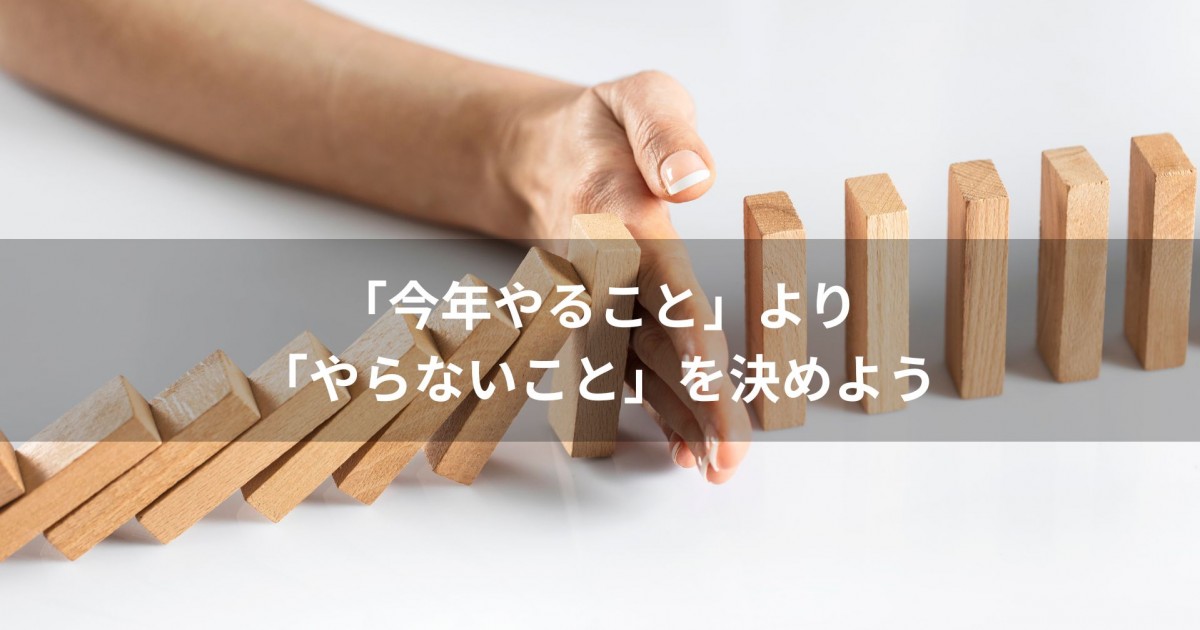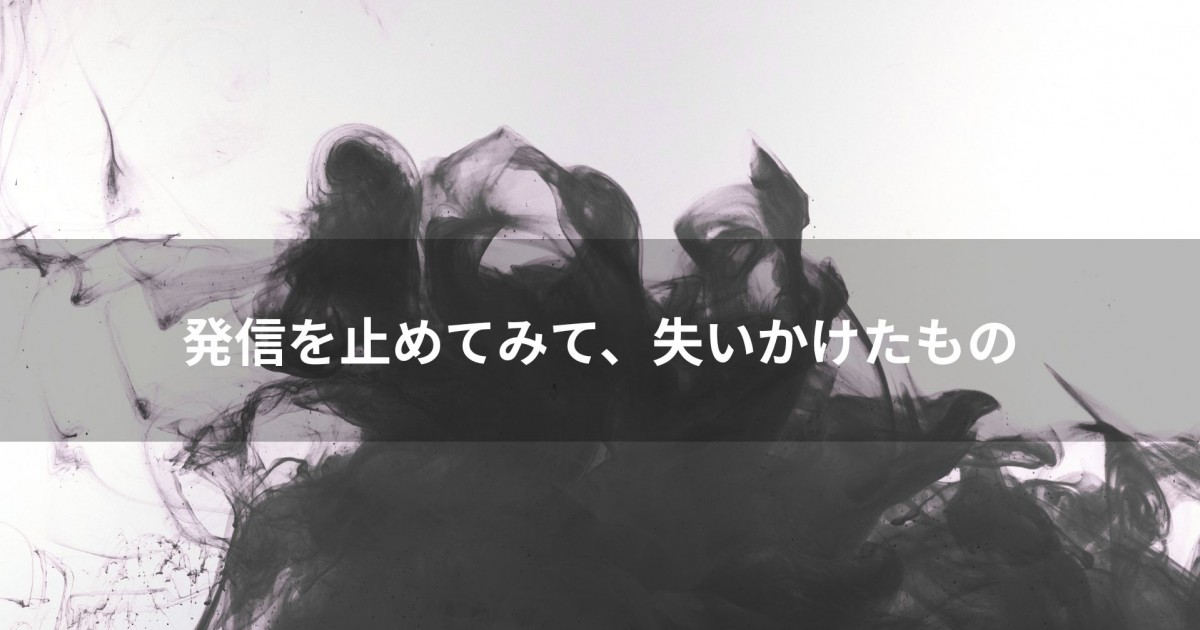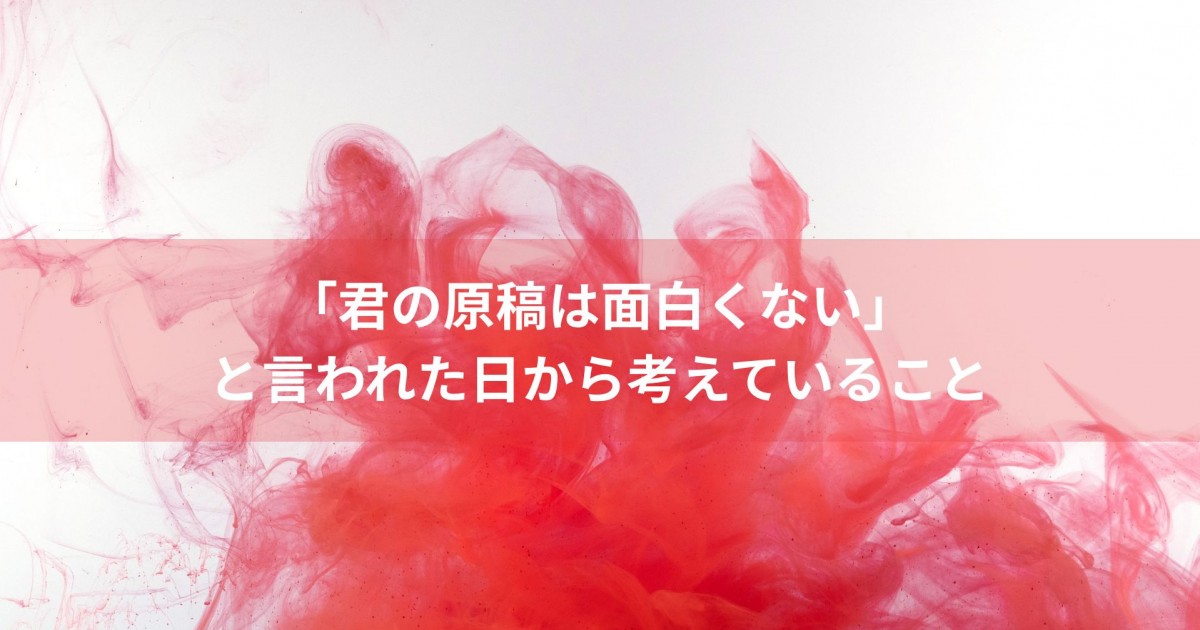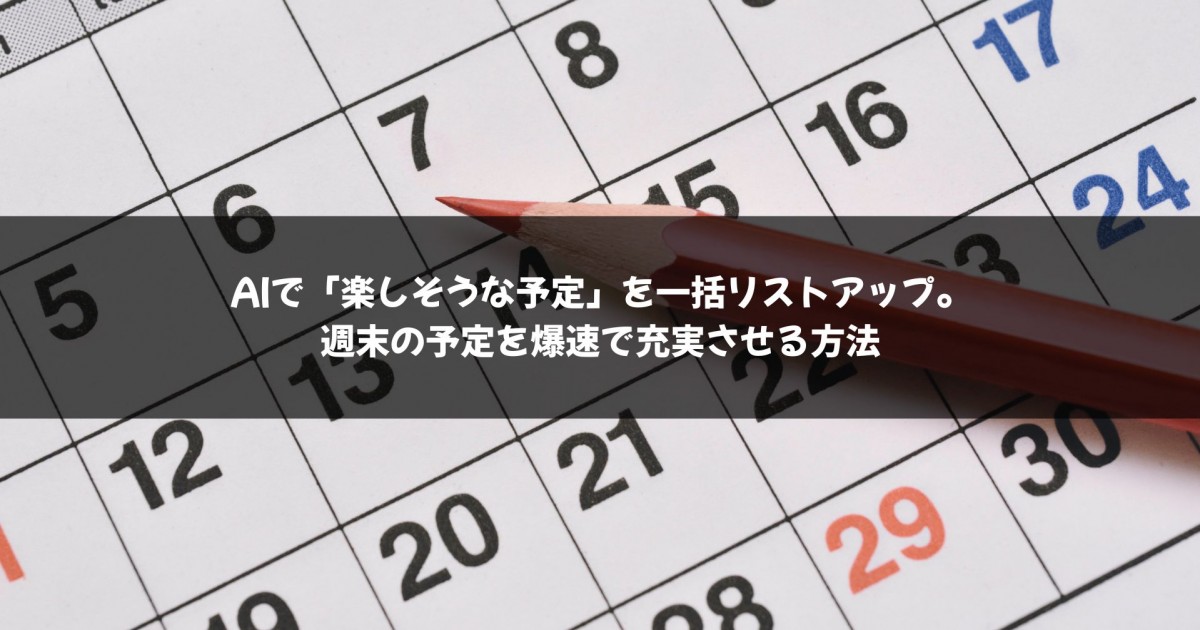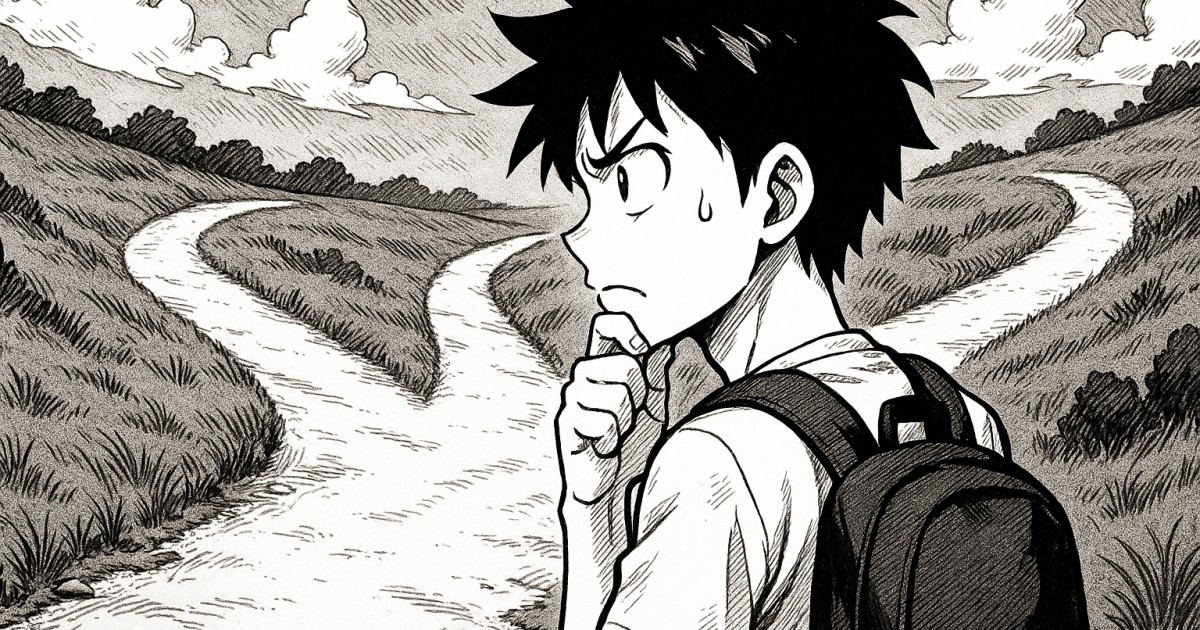AIでライターや編集者が「失う力」と「得る力」
おはようございます、まむしです。9月1日の月曜日。みなさまいかがお過ごしでしょうか。
先日、Xをパトロールしていたところ、思わず目を止めてしまった記事があったのでご紹介させてください。2025年8月に New England Journal of Medicine(NEJM) に掲載されたレビュー論文を扱ったもの(How can medical trainees use AI without losing critical thinking skills?)で、テーマは「AI時代の医学教育について」。
医学分野の話ではあるのですが、概要を読み込んでいくと「すべての職種に当てはまる話では…?」とも感じたので、ここで紹介します。
AIによって生じる、人間の力の衰え
今回のレビュー論文では、AIが医療現場や教育に浸透する中で、若手医師のスキルが育たない、あるいは失われていくリスクが、3つの方向から整理されていました。
-
Deskilling(考える力が衰えてしまうリスク)
-
Mis-skilling(間違った情報をそのまま吸収してしまうリスク)
-
Never-skilling(そもそもスキルが育たないリスク)
分かる、ような気がする。
というか、多くの場面で語りつくされているような内容だと思うのですが、ひとくちに言えば「AIに頼りすぎると、そもそも“自分で考える経験”を積まなくなってしまう」ということだと感じます。AIを使うことで一見、効率化されているように見えても、裏では思考のプロセスがショートカットされていて、学習の土台そのものが抜け落ちてしまうリスクは確かに存在する。
ライター・編集者に置き換えてみて、自分自身もなんとなくそんな気はしていたのですが、便利さと引き換えに、自分の“書く筋力”や“問いを立てる力”が少しずつ削られているのだとしたら…と考えると、やっぱり注意しなければなとも思いました。
ちなみに医学系では最近こういうトピックが続いていて、数週間前にもこんな記事(海外記事の日本語訳版)が紹介されていました。AIを導入した医師たちが、数カ月のうちに(AIを使わない状態での)“腫瘍の発見率”を大きく落としていたという内容です。
■AI時代に批判的思考を守る5つの動作
では、どうやって「思考力の低下」を防げばいいのか。今回の論文レビューでは、それに対する実践的なフレームワークとして、「DEFT-AI」という5ステップが提案されていました。