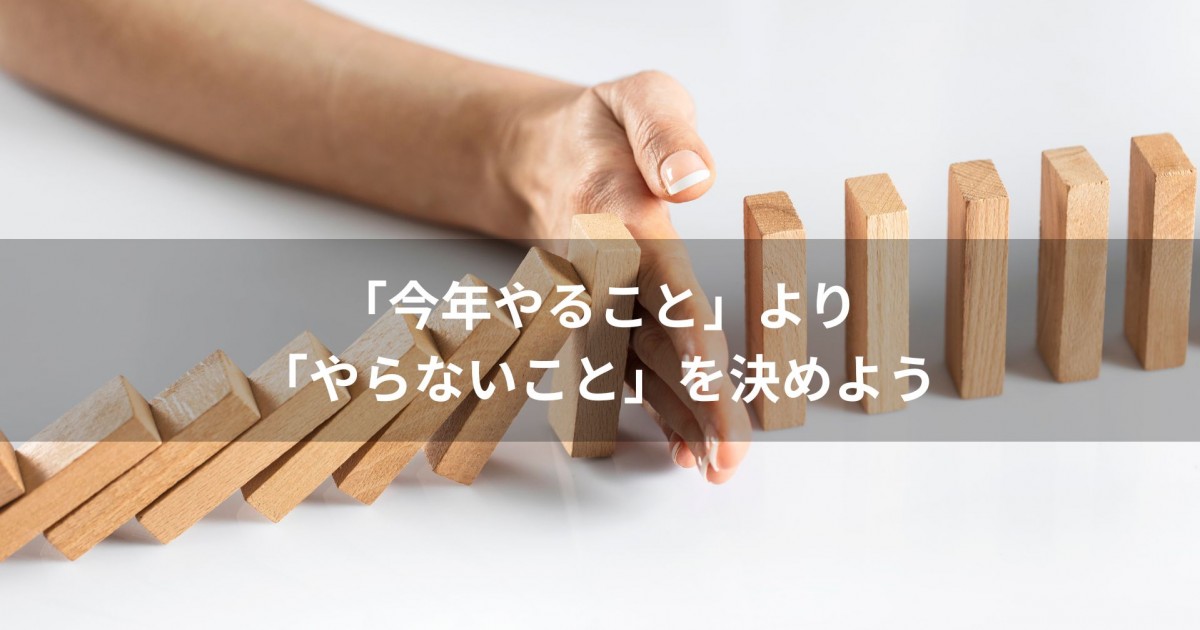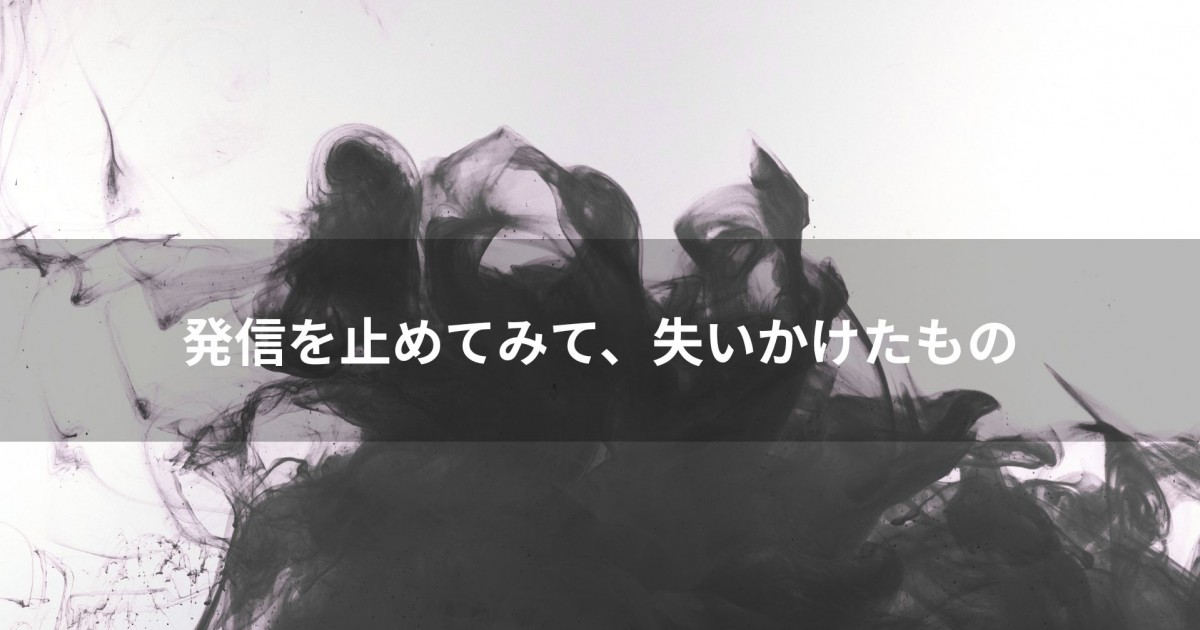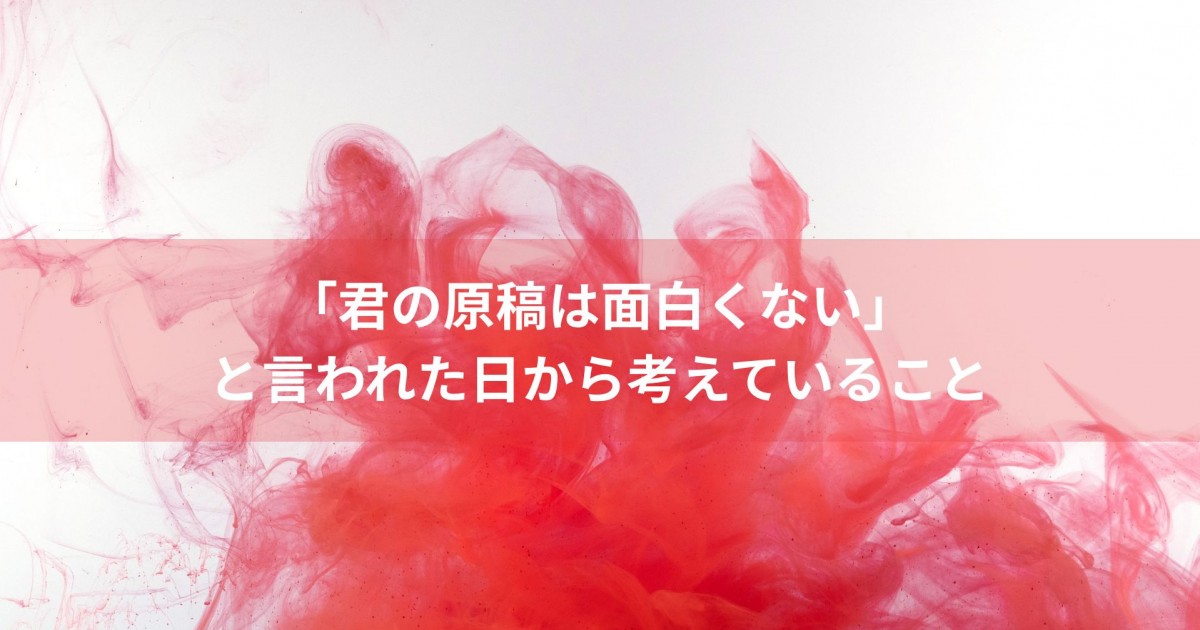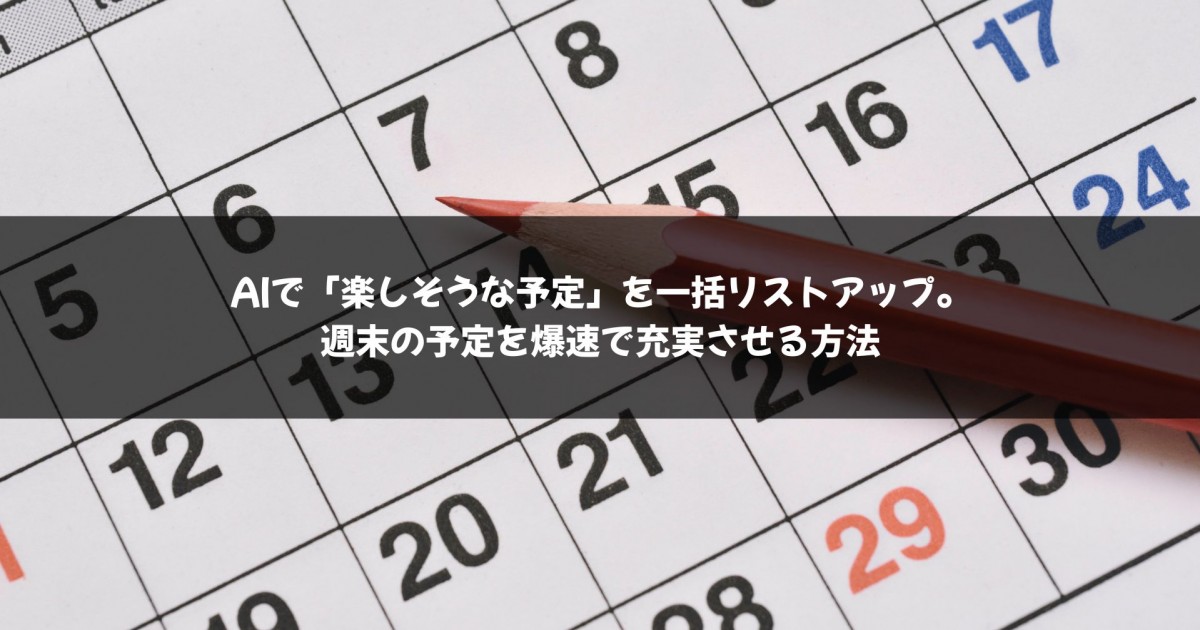”何かの専門家”たちがライターに進出。そのとき、「何者でもない人」の戦い方
このニュースレターでは、ライターや編集者はもちろん、発信に関心のある方々の日常がちょっと豊かになる情報を毎週流していきます。ご興味あればぜひご登録くださいませっ。
【目次】
-
現場の専門知識を持った人が「ライター」に。 強い専門性がないライターはどう戦うか。
-
何者でもない人の強み1,2,3
-
「できないこと」ばかりが目に付くときは
ぼーっとしてたら先週配信するの忘れてましたすみません(今週は出さないんですか?と聞いてくださった方ありがとうございます!めっちゃうれしかったです!!)。イベント登壇の機会を色々いただきあたふたしておりました。最近リアルで登壇する機会をいただくことが増えてきたのですが、そこでいろんな方とお話しする機会をいただくと、「そんな論点があったか!」とすごく気づかされますし、発信のモチベーションが高まります。
直近では2回、セミナーや飲み会があったのですが、その2回ともで議論に上って盛り上がったテーマがあったので、今回消化させていただきます。
◆現場の専門知識を持った人が「ライター」に。 その時、強い専門性がないライターはどう戦うか。
↑お題としては、コレです。
クラウドソーシングや副業も一般的になってきましたし、AIによって多くの人が発信力を増強していくことが想定されます。そうすると、今まではライターが専門家を取材して記事にする、という形だったところが、専門家自身がダイレクトに発信できるようになる。そんな社会でどう、既存のライターが生き残っていけるのか、という話しです。
これは本当にそうで、僕も医療業界で記者・編集者をしてきましたが、最近では医師・看護師・薬剤師免許などを持って現場で活躍してきた方が、ライターとして活躍するケースがそんなに珍しくありません。専門知識もさることながら、現場の肌感や原体験もある方が多いので当然ながら頼りになります。一方ぼくはというと、何の医療資格もないですし大学も文系学部なので、こういう市場において何を強みととらえているのか、というのが今回のお話です。
僕自身、このテーマについては20代のころから本当に悩ましく思っていて、諸先輩方にもまさに相談して回った時期を乗り越えて今があるので、N=1の事例ではありますが、同じように悩んでいる方の参考になればうれしいです。
この記事は無料で続きを読めます
- ## 何者でもない人の強み1:偏差値30の人の気持ちがわかる
- ## 何者でもない人の強み2: フラットに人脈がつくれる
- ## 何者でもない人の強み3:メディアを作る力
- ##「できないこと」ばかりが目に付くときは
すでに登録された方はこちら