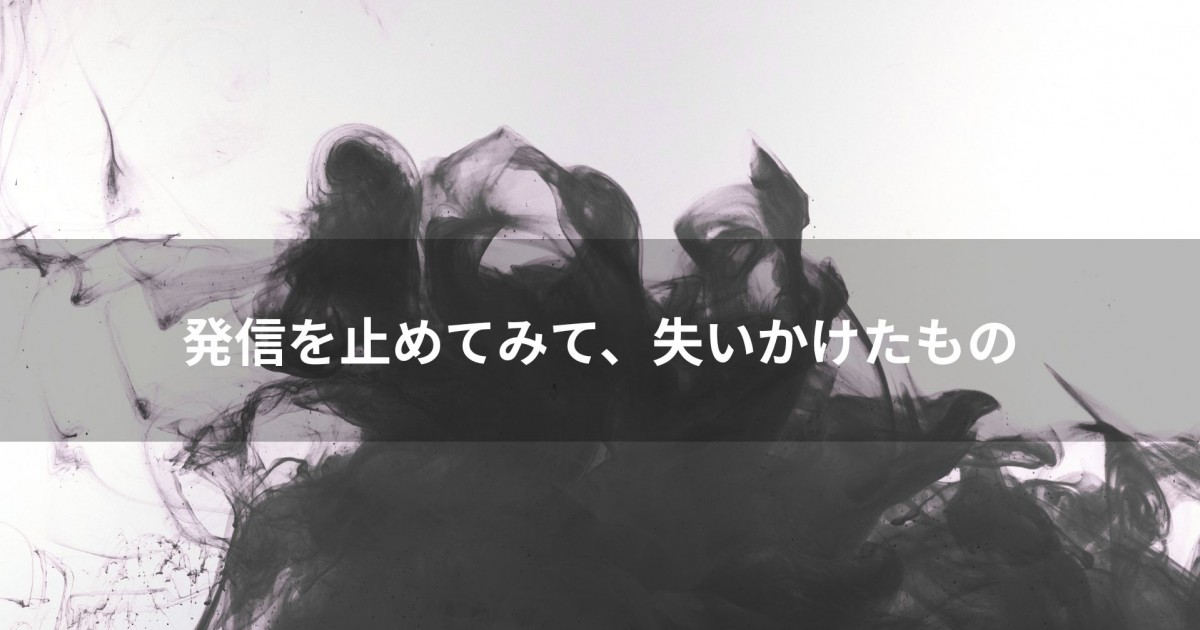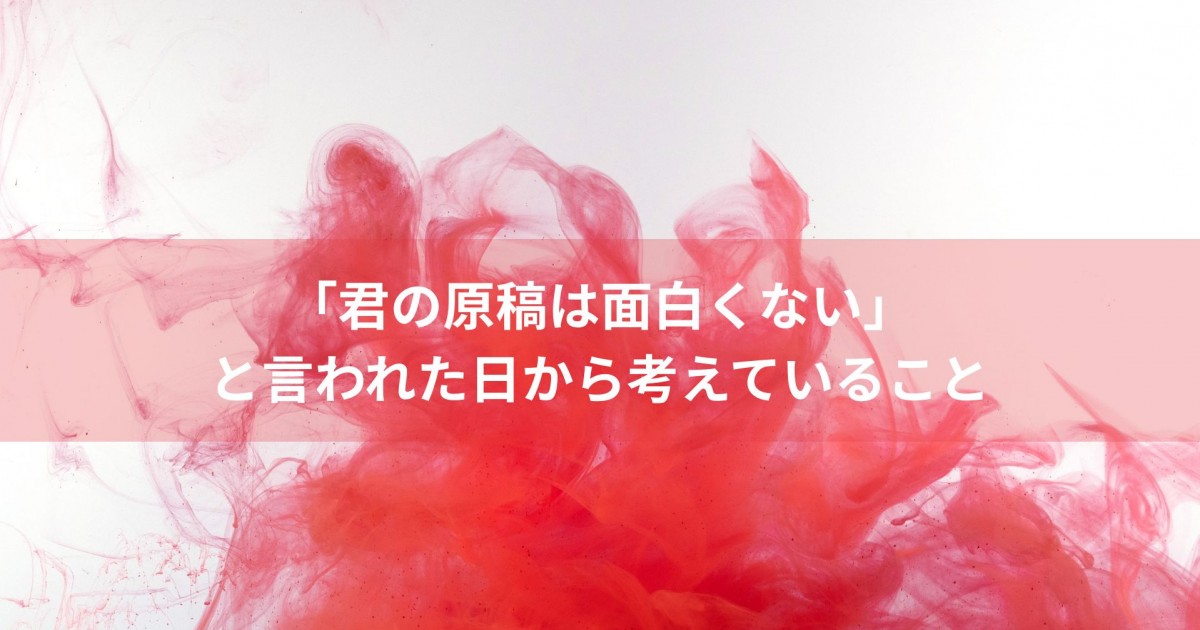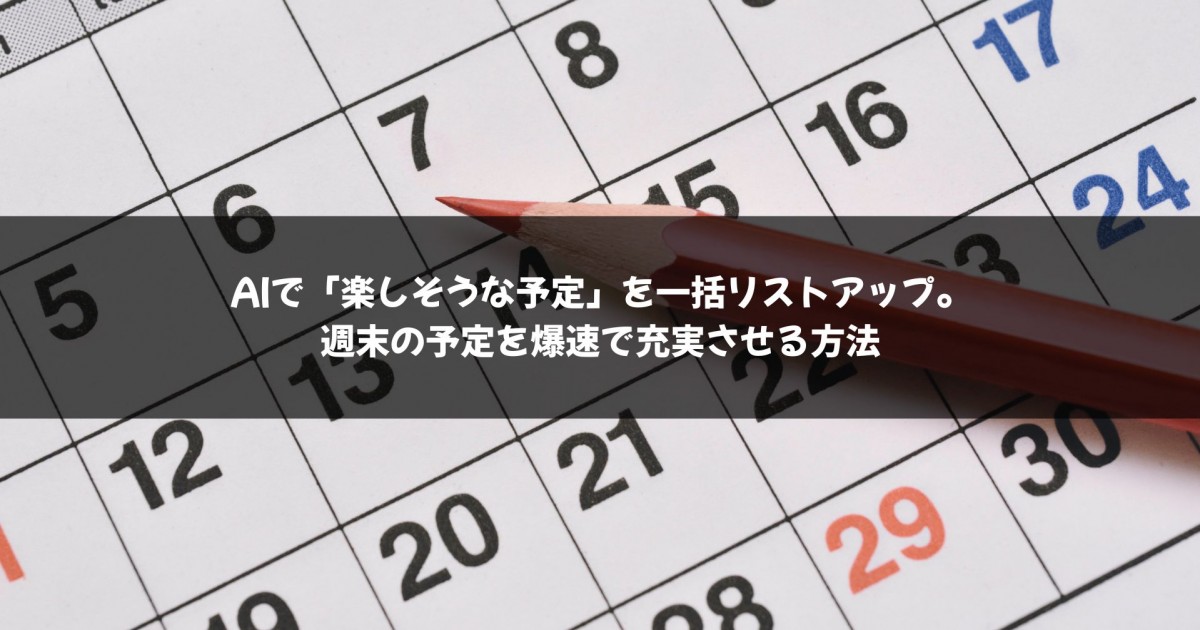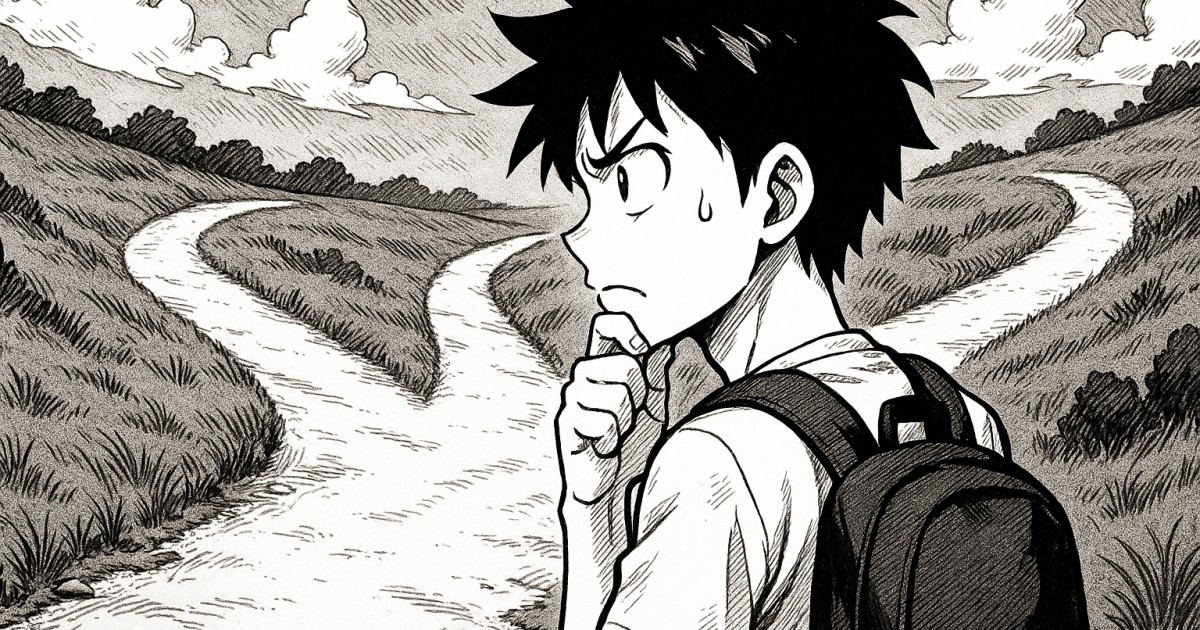ブレスト会議の質を高めるためにだいじなこと
アイデアが浮かばなかったり、行き詰ったときの「ブレスト会議」。人に話を聞けば何かの突破口になりそうな期待感はありますが、いざやってみるとファシリテーションが難しかったり、話してすっきりするだけで実効性のある企画につながらないこともあるような気がします。
今回は、ブレスト(壁打ち)をより価値ある時間にするために意識したいこと、特にファシリテーターの立ち回りや流れのつくり方について整理してみたいと思います。

ブレスト=壁打ちの重要性
自分のアイデアでは何ともしがたい状況は、誰にでも起こり得ます。そういう時に頭の中にある“もやもや”を誰かに向かって言葉にしてみることで、思いがけない発見があったり、自分の考えの輪郭がはっきりしてくることがあります。
完成された企画を持ち寄るのではなく、未完成なアイデアの“途中”を見せ合う。そんな不完全な状態を歓迎する空気が、閉塞感のある状態では特に必要です。
発散と収束のバランス
ただ、「単に集まってアイデアを出しましょう」と言うだけでは難しい。その難しさの原因は「発散と収束」のバランスにあるように思っています。
「イマイチなブレスト会議」の代表例は、「発言がなかなか出てこないこと」。参加者が「最初から正解を出さなきゃ」と身構えてしまったり、発言そのものに緊張してしまうと、会議自体の存在意義も薄れてしまいます。
これとは対照的に、「とにかくアイデアが散らばって収束できない」という失敗ケースもありがちです。ストレス発散やコミュニケーションの場としては意味があるものの、時間だけが過ぎてしまい成果につながらないと、物足らない気持ちになることも多いのではないでしょうか。
そういう風に考えるとやっぱり、「発散して、何かにたどり着く」ための流れづくりが重要になるのを感じます。
揃える前提と揃えない前提
上記のような失敗ケースを避けるためには、「前提をそろえておくべき個所」と「自由度を持たせるべき個所」を意識的に分けることが大切です。
【揃えるべき前提】
たとえばコンテンツの壁打ちなら、「誰に届けたいのか」「どんな状態になってほしいのか」は、必ず先に共有し、ここからはぶれないようにする。発散しすぎた時も「そのアイデアは今回の目的にあっているか」という具合に立ち返れる場所を最初に示しておくことが、とにかく重要です。
僕もよくブレスト会議に読んでいただくことがあるのですが、そういうときも最初の数分は「このブレストで所与の前提条件として飲み込んでおかないといけない部分はどこなのか」を探る作業にめちゃくちゃ意識を割いています。
【自由度を持たせるべき個所】
こちらもコンテンツで言えば、コンテンツの内容は勿論、表現方法や切り口など、どの程度のところまで自由に議論してよいのかは意識しています。
いろんなブレスト会議に出て話を聞いていると、「どこまで自由に発想してよいのか」という解釈部分に、意外と個人差が大きいことを感じることがあります。前例を気にしすぎていたり、現在の体制でできる範囲内に思考が狭窄していたり、常識にとらわれていたりすることが結構あるので、特に若手人材の話を聞くときはこのあたりの「自由に発想してよい幅」のチューニングを行うだけで良い意味でタガが外れ、本人の潜在能力を高められる印象があります。
事前に「宿題」を出しておくことの効用
上記のように「そろえる前提」「自由度を持たせるべき個所」を決めたら、できれば会議前に「宿題」を課しておくのが結構大事なように思います。ブレスト会議といっていきなりその場でアイデアを求められても、その場でパッと出せる人とそうでない人には差がありますし、思考投入レベルが違う状態で意見しあうとすれ違いが起こることがあるからです。
たとえば:
-
「考えているアイデアを1行で書いてきてください」
-
「今回の目的に合いそうな既存コンテンツを1つ探しておいてください」
みたいな小さな準備だけでも、当日の思考投入レベルが格段に揃います。「前提条件」「自由度を持たせるべき個所」を共有したうえで、助走期間的に宿題を課しておくと当日の議論のクオリティも高まるのでお勧めです。
会議中のファシリテーターの立ち回りが鍵
壁打ちが実りある時間になるかどうかは当然ながらファシリテーターの立ち回りに大きく左右されます。「今は議論を発散させるフェーズなのか、収束させるべきなのか」「目的の再確認が必要なのか」など、議論の現在地を見失わないことが大切です。
以下、ファシリテーターとしてそれとなく(?)立ち回るうえで、僕が意識しているポイントをいくつか挙げてみます。