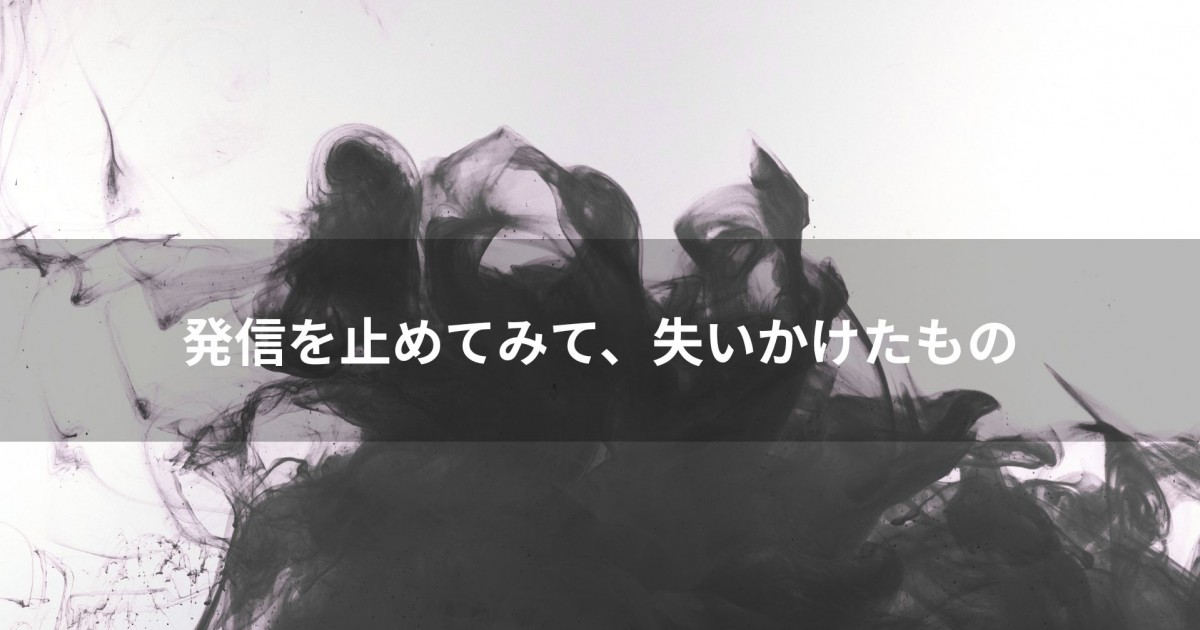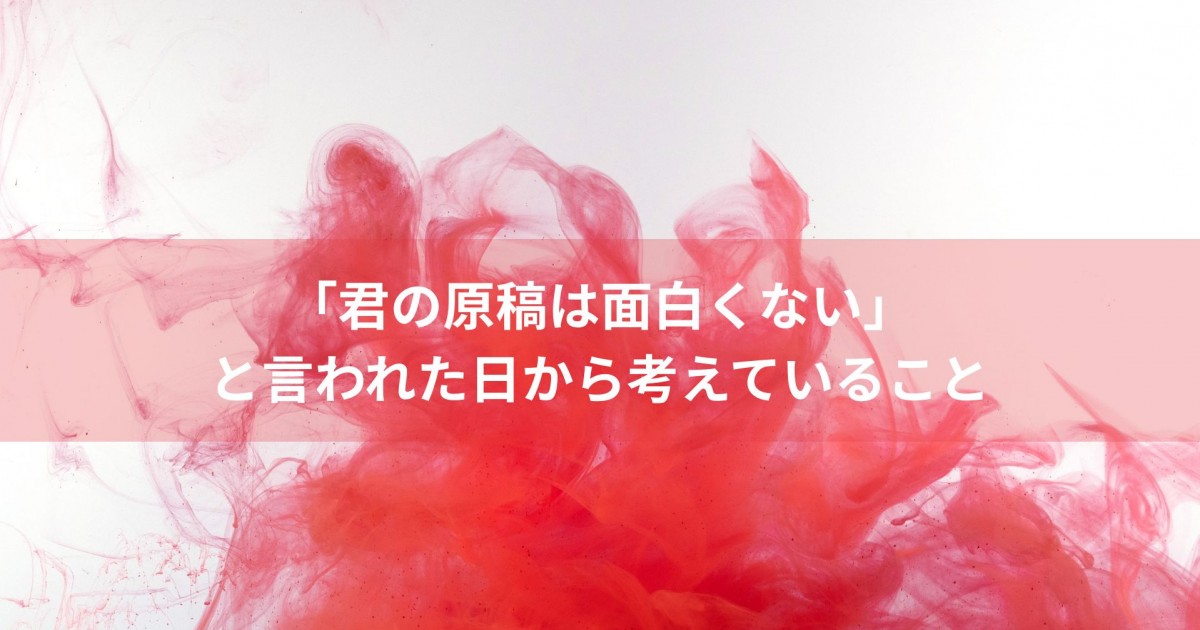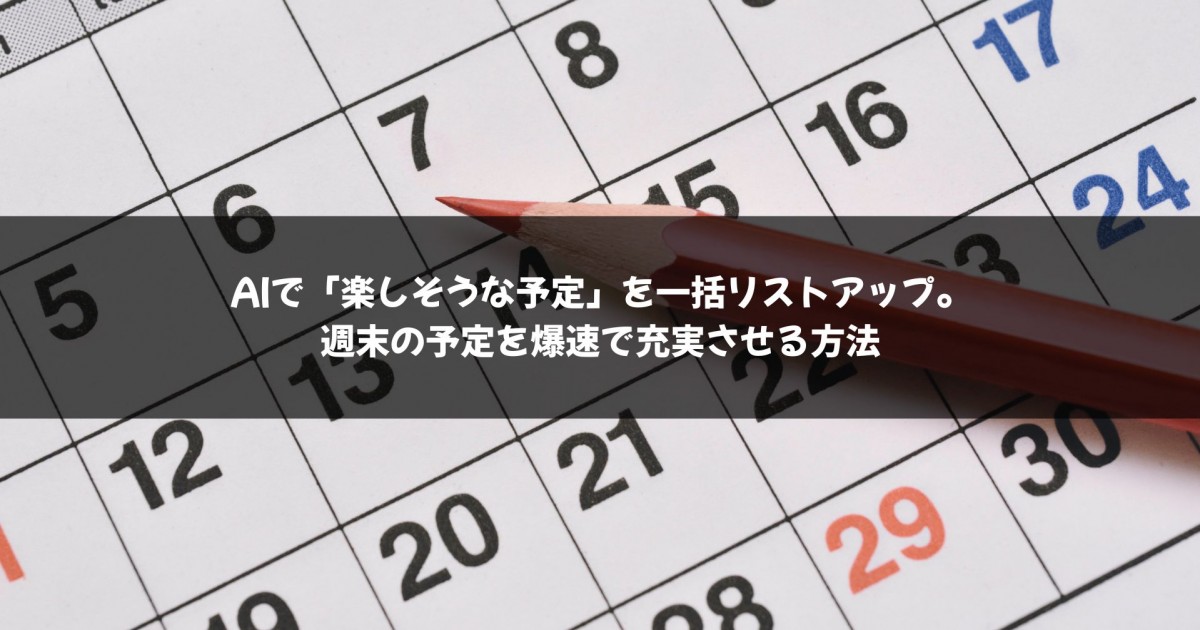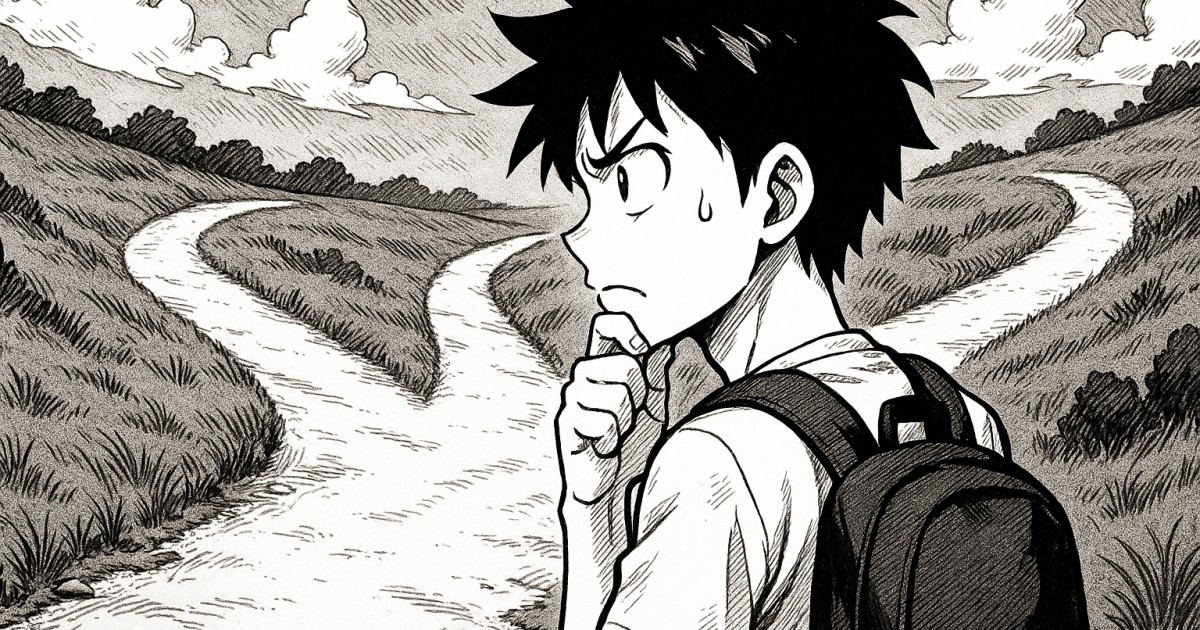優秀な人が「見えないところで何やってるか」気になる時代
※※※※※※
最近、本屋をふらっと歩いていると、「すごい人が、見えないところでやっていること」といったタイトルの本をよく見かけます。 「一流の人はこうしていた」「成功者の舞台裏」──そんな“裏側”に光を当てた書籍が平積みになっているのを見ると、“見えない取り組み”に強い関心を持つ人が増えているんだなと感じます。
SNSで他人の成功体験ばかりが大量に流れてくる今、「本当はどこで差がついているのか?」を知りたくなるのは自然なことかもしれません。
ただ、同時にすごく思うのは、「いっしょに働く人の“見えない部分”が、昔よりも見えづらくなっているのかもしれないなぁ」ということです。
「背中を見て学ぶ」ができた時代
少し前までは、先輩の「仕事の仕方」が、もうすこし自然と見えていました。
洗練されたカリキュラムこそなくても、「見て学べ」という風土はあり、オフィスにいれば、誰がどんな段取りで仕事を進めているのか、どこで詰まり、どこで工夫しているのかが、なんとなく伝わってきた。「昨日、遅くまで残ってた先輩、何してたんだろう?」と気になってのぞいてみると、びっくりするくらい丁寧に資料を直していたりして、「ああ、こういうところで差がつくのか」と納得する。そういう“観察による学び”が、日常のなかにありました。
僕自身も、先輩のそうした姿勢を見て、何度も襟を正されてきました。表に出ない泥臭いプロセスや、試行錯誤の積み重ねを見て、「自分もちゃんとやろう」と思えたことが何度もあります。
けれど、そうした風景はどんどん減ってきました。 リモートワークが珍しくなくなり、フリーランスや副業など、チームの構造も働き方も分散しています。働き方改革で業務時間外の行動には明確な線引きがなされ、残業しながら上司と2人で黙々と作業する…みたいな光景も少なくなっているように思います。
こうして、「近くにいれば、なんとなく伝わる」という状況が減り、「距離」が物理的にも情報的にも広がった。これは決して悪いことではありません。というかむしろ、健全な変化だとも言えるからこそ、対処しようのない状況に「これでいいのかな」と、モヤっとするんだと思います。
「学び合い」がしにくい編集・ライターの現場
編集やライターの世界もまた、こうした悩みに直面しています。
もともと育成モデルが多種多様で、正解がひとつではありません。ある人は出版社で叩き上げ、ある人はSNSで名前を売り、ある人は独学で一人前になっていく。それぞれのスタイルがあるからこそ、「他の人がどうやって成長しているのか」が、かえって見えづらくなっている面もあると思います。
加えて、組織のあり方も変わってきています。 編集部の中核に正社員がいて、そこにフリーランスのライターや業務委託ディレクターが加わる──そんなチーム構成は、いまや当たり前になりました。けれど、物理的な距離だけでなく、関係性の中にも“見えにくさ”が生まれがちです。 どんな背景で判断しているのか、どこまで踏み込んでいいのか。暗黙知や信頼のベースが築きにくいからこそ、「共同作業をしながら学ぶ」ことが、以前に増して難しくなっているのかもしれません。
たとえば、隣の人がどんな順序で原稿を書いているのか、どこで悩み、どう突破しているのか。
そうした“作業の要諦”が共有されにくくなっています。 結果、HowToやテンプレートはあっても、現場の勘所や「詰まりポイント」は言語化されず、誰かの中に埋もれたままになってしまう。
また、「この人のようになりたい」と思える編集者やライター像が見えづらく、自分が1年後、3年後どうなっていたいのかが想像しづらい。 ロールモデルが見つけづらいし、仮にロールモデルらしき人を見つけたとしても、そこに向かうために何をすればいいのか分からない。
こうした「学びの接点の希薄さ」が、働き方の進化とともに静かに進んでいるように思います。
「見えない時代」の学びを取り戻すために
では、どうしたらいいのでしょうか。
ひとつは、「見えないものを、自分から見に行く姿勢」を持つことなんだろうなと思います。
「すごい」と思ったライターや編集者が、どんな仕事の順序で動いているか、雑談の中で聞いてみる。1on1で「最近、工夫していることはありますか?」と尋ねてみる。 見えないことを「わからない」で終わらせず、ちょっとだけ踏み込んでみるだけでも、得られるヒントはあります。
もうひとつは、「見えないことを、少し見えるようにしてみる」こと。 自分がどうやって考え、悩み、行動したかを、簡単にでも言語化して周囲に伝えてみる。改善点を誰かが指摘してくれるかもしれませんし、自分の工夫を共有することで、誰かにとっての“非公式マニュアル”になるかもしれません。これは僕自身も仕事をしていて思うのですが、「教えてもらいたい雰囲気」を出しているかどうかってめちゃくちゃな個人差があるんですよね。「フィードバックを積極的に受け止め、成長に活かす意欲」を示すことも、(もしそれを望むのであれば)意識的にやったほうが良いんだろうなと思います。
「見えない努力」が気になる時代というのは、努力がより個別化し、働き方が多様になった時代でもあります。 そのなかで、「他人から学ぶ」「誰かの姿勢を真似する」という営みを絶やさないためには、見る側の工夫と見せる側の工夫、両方が求められているんだろうなぁとおもうこの頃です。

ライターや編集者の育成については個人的にめちゃくちゃ課題意識があり、今後も掘り下げていきたい…のですが、こういうのって「問題を掘り下げるだけ」ではぜんぜん意味がなくて、きちんと何かやらなきゃダメなんですよね。
僕一人では知見的にも体力的にも限界はあるので、緩やかにでもよいので何かアクションをとり続けたいなという気持ちがあります。何かアイデアや協業案のある方がいたらぜひ!
\無料のランチセミナーに出ます/生成AI×編集力で実現する無理なく続ける発信のコツ
6/10にカラーミーショップさんのランチセミナーに登壇させていただきます!
ネットショップを運営されている方向けの内容ではありますが、広くコンテンツマーケティングに携わっている方や、ライター編集者の方にも通じる話にはなりそうなので、ご興味があればぜひ!

日本最大級のフリーランス向けウェブメディア「Workship MAGAZINE」さんでもいろいろ書かせていただきました!5月は、「大手との取引で気を付けるべきこと」「ライターや編集者の方がやってしまいがちなケアレスミス」についてそれぞれ取り上げておりますのでぜひ読んでいただけると嬉しいです!!(そしてSNS感想をもらえるともっとうれしいです!!)
すでに登録済みの方は こちら