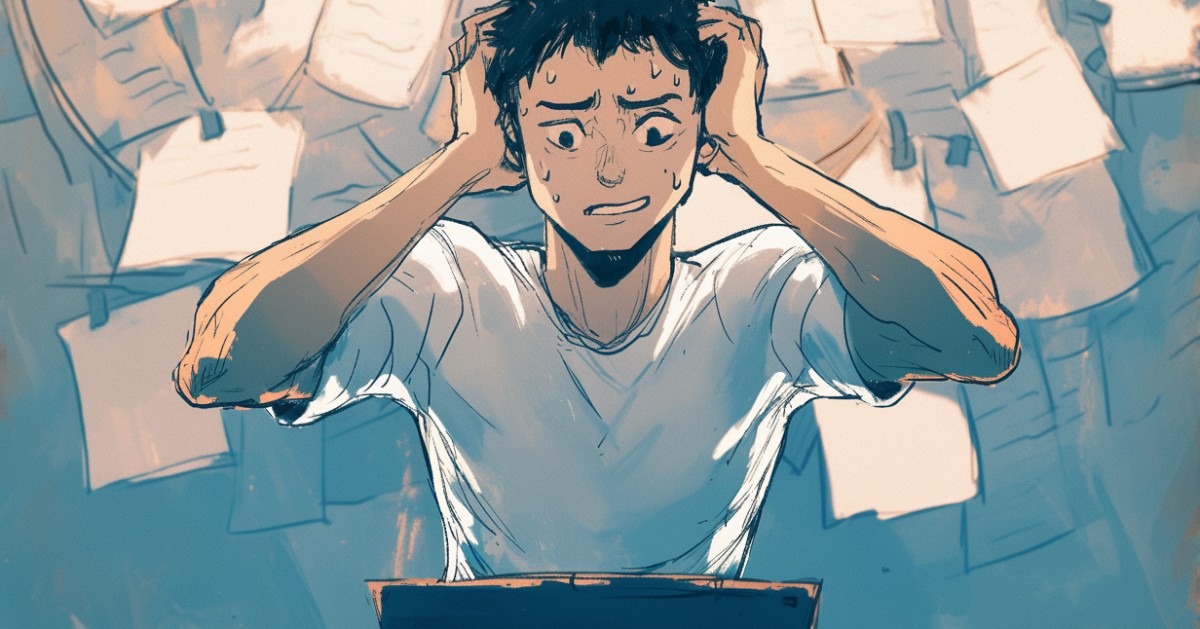フルリモート環境で、僕が生産性を高めるためにやっていること

ライティングや編集のお仕事って、リモートワークとの相性がめちゃくちゃいいですよね。お気に入りの作業環境で仕事ができるのは大きなメリットである反面、孤独感が募ったり、SNSに没頭して閉塞感にさいなまれたりなどの副作用もあるように感じます。僕も今、ほぼフルリモート状態で働いているのですが、仕事の環境を整えるためにやっていることについて書いてみようかなと思います。
※リンク先のAmazonページは、Amazonアソシエイトのリンクへと遷移します。
作業環境は“ひとつの場所”じゃなくていい
リモートワークが当たり前になってきた今、「どこで働くか」は単なる環境の話ではなく、自分のパフォーマンスを左右する大事な要素になっています。特にライターや編集者のように、思考力や集中力がものを言う仕事では、作業環境のちょっとした違いがアウトプットの質に大きな影響を与えます。
僕自身、ここ数年フルリモートで働いてきて感じるのは、「最適な作業環境」はひとつに決める必要はないということ。もっと言えば、すべての作業をひとつの場所で完結させようとしないほうがうまくいくことが多いようにも感じています。
たとえば、アイデアを練るのは散歩がいい。でもそれを文章に落とし込むなら、静かな部屋が最適。そんなふうに「発想する場所」と「形にする場所」を分けるだけでも、驚くほどラクになるし、結果的に質の高いものが書けるようになります。
以下はあくまで「僕の場合」です。雑音があるほうが集中できる人・できない人がいるように、作業環境って個人差が大きいので、ご自身に置き換えて考えていただければと。

なお、僕の場合、散歩したりお風呂に入ったりしながら音声メモでアイデアを残して構成を整理し、午後の静かな時間に執筆し、翌日の午前中に集中して仕上げる、というように、作業フェーズごとに環境やリズムを変えることもあります。
「シチュエーションを使い分ける」という発想がすごく大事な気がしており、会社員の場合だと「こういう日は出社」とか決めてやるのもありなんでしょうね。ほんと、働く場所を選べるのがこんなにもクリエイティブだとは。
「どのフェーズに重きを置くか」で作業環境は変わる
そのうえで、自宅の職場環境をどう整えていくか、です。
まず、ライターや編集者と言っても、全員が同じように仕事しているわけではありません。前述の「発想→構成→執筆→仕上げ」のどのフローの中で、どの箇所に一番適した環境を作るかが、一つポイントになるような気がしています。
僕の場合、執筆をはじめ「一人で黙々作業する時間」が多いので、デスク回りはすごく無機質な感じ。これだけ見ると「めっちゃ普通じゃん」と我ながら思うのですが、定常配置するのは最低限にしてデスクのスペースを確保し、その時の作業特性に応じて好きなように机上を使えるように意識しています。

こうしてみるとシンプルすぎて、マジで他愛ないですが、極力デスクには何にも置きたくない!コードも最低限にしたい!という意思はあります
発想を高めるリモートワーク術
発想に極振りするなら、音声メモを活用したり、マインドマップを描いたり、通勤電車でメモアプリにキーワードを書き留めたりと、場所を選ばずアイデアをキャッチできる環境を整えましょう。
僕の場合自宅でも、ソファでくつろいだり、お風呂に入ったりしながら音声AIアプリでメモを取ったりして、「発想」に力点を置いた環境を作るべく工夫をしております。アイデアを練るという意味では、オンライン会議への参加環境もあるなあと思っており、昇降デスクを導入し、立って(集中して)会議に参加できるようにもしてみたり。

それにしてもChatGPTって便利ですね
あと、発想って気分転換が大事だと思っていて、リラックスできる環境をつくる意味では、五感に働きかける工夫も効果的だとも聞きます。
僕の場合、こういうスティックタイプのアロマを持っていて、気持ちを切り替えたいときによくクンクン嗅いだりしますし、アレクサに「カフェミュージックを流して」「焚火の音を出して」と作業音を流してもらったりして、気にならない程度のBGMを流すようにしてます。あと、PCの真横に電子ピアノがあり、ぼーっとしたいときにいつでもピアノが弾けるようになっています(そんなリラックスしている僕の様子をAIで生成してみますが、なんかとてもヤバイことやっているように見えますね)。

マジで見た目やばいですね
構成作業を効率化させるリモートワーク術
構成フェーズでは、アイデアを整理・可視化できる環境が重要です。大きなホワイトボードで章立てを組み立てたり、付箋を使って情報を動かしながら全体像を把握したり。この辺の作業、iPadでもできるんじゃないかといろいろ試したのですが、iPadには誘惑が多いので、結局手書きで情報を整理しちゃってます。
アナログ作業でもいいっちゃいいのですが、紙の作業が増えるほど机の上って汚くなりがちなので、そこだけ要注意。マグネットで机にくっつくごみ箱・シュレッダーで、なんとかデスクの秩序を守っております。

情報の一覧性・視認性とかではやっぱ、紙って強いですよねえ。
執筆をはかどらせるリモートワーク術
執筆時は、外界との接点を最小限に抑えた没入環境が効果的です。まず、チャットツールの通知はオフにして集中モードに。XなどのSNSにもアクセスしないようにして、画面には執筆中の原稿だけを表示して、余計な情報を排除することで、文章に没頭できる状態を作り出します。
僕の場合、執筆やデータ分析の時間が結構多いので、マウス・キーボード・ディスプレイには試行錯誤を重ねました。そういうのに詳しい界隈の方々からすると定番ガジェットではあるのですが、次のラインナップに落ち着きました。
そうそう。一時期はトリプルディスプレイも試してみたですが、ディスプレイが多すぎると注意が散漫になって逆に執筆が遅くなる自分に気づき、デュアルディスプレイへと戻しました。そのとき、モニターアームが一本余っちゃったんですが、そこに受け皿みたいなのを取り付けて、iPadやら資料やらを置けるようにしてみた結果それなりに良かったです。
編集がはかどるリモートワーク術
編集のフェーズでは、細かな修正や校正に集中できる環境が必須です。↑でもご案内した大きめのディスプレイで全体を見渡しながらフォーマットを整えたり、紙に印刷してじっくり推敲したり。この辺は、ここまでで紹介したグッズが役に立ちます。
あとはやっぱり、最近はAIですね。。上記のキーボードにはスマートオプションという機能があり、AIへのアクセスを高めることができるので、そういうのも組み合わせながらやってます。物理デバイスとAIなどソフトが組み合わさるとマジで強いっす。
なんかマジで趣味っぽく書いてしまいましたが、作業環境とは、単なる場所ではなく、思考と感覚を支える"舞台装置"だなあと思います。各フェーズに適した環境を意識的に選び、切り替えることで、アウトプットの質は確実に向上していきます。皆さんのおすすめも教えてください!
【ご紹介したものたち】
・電動昇降式デスク
・スティックタイプのアロマ
・Amazon Alexa
・マグネットで机にくっつくごみ箱
・ディスプレイ
・キーボード
・マウス
・モニターアーム
・モニターアームにつけるパソコントレイ

リモートワークは自分で作業環境を選べるのがとても良いですよね。デスクツアーを見るのが好きでつい、Youtubeなんかでも眺めてしまいます。皆さんもなにかおすすめがあればぜひXなどでも感想とともにつぶやいてください!
今回は「生産性をどう上げるか」みたいな視点でしたが、リモートワークの課題として、「孤独感を覚えやすい」「滅入りやすい」とか、メンタル面での課題があるようには思っており、また機会があれば、リモートワーク下のメンタルの保ち方についても紹介してみようかなと思っています。

すでに登録済みの方は こちら