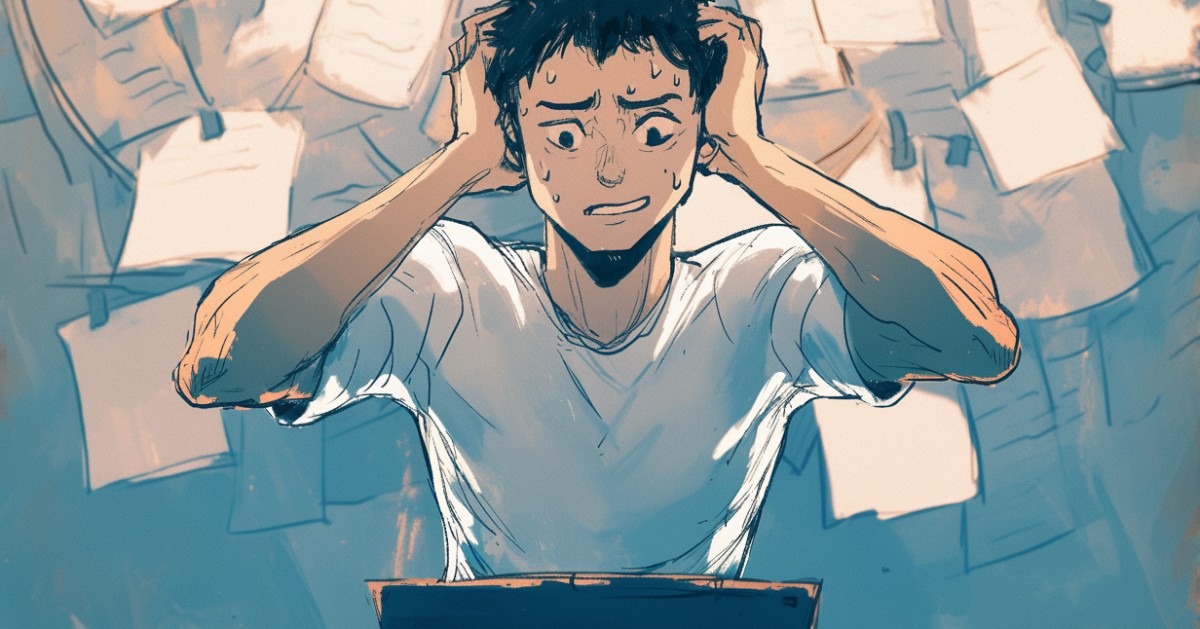遺書を書くような気持ちで発信する

僕の発信をすべて学習させたAIに、記事を書いてもらうことってできるんだろうか。そんな風に思って、自分の過去のnote150本、膨大なXのつぶやき、ニュースレター70本、書籍の内容などなど、思いつく限りの過去のアウトプットを盛り込んだ「AIまむし君」を作ってみました。
たぶん、控えめに見積もっても読み込んでいる文字数は50万文字以上にも及ぶ「AIまむし君」。
さっそく質問してみました。
まずはシンプルに、「企画の立て方が分からないです」と。
■そして出してくれた回答がこちら
■「明日やろう」は、もう卒業
「企画が浮かばないんです……」
これはもう、編集者・ライター界隈で聞き飽きた悩みのひとつかもしれません。
僕自身も後輩や仲間から何度となくこのセリフを聞いてきました。そして正直なところ、僕も時折そうなります。そう、「企画って、天から降ってくるものじゃない」んですよね。
特に中堅になればなるほど、「変な企画出したら恥ずかしい」とか、「これくらいじゃ弱いな」なんて自意識が邪魔して、ますます手が止まりがちになります。
でも、それって本質的な問題じゃないんです。
■「考える」よりも、「集める」
企画が出せないとき、多くの人は「考えが足りない」と自分を責めてしまいます。
でも実は、企画が出せない原因は「考える力」ではなく「集める力」、つまり事前の情報収集の不足なんじゃないかと僕は思っています。
例えば書店に行ってみる。専門分野の棚の並びを眺めて、「今、読者がどんな情報にお金を払っているのか」を探る。月に1回の書店巡りを習慣にしている僕としては、これだけでネタ帳が埋まるほどのヒントをもらえることもあります。
さらに、セミナーサイトやSNS、統計データ、リアルな読者との会話――こうした多角的なインプットを日常的に積んでおけば、「さあ、企画を考えよう」と机に向かったとき、すでに材料が手元に揃っている状態になるんです。
■3つの「円」を意識する
情報収集だけじゃなくて、それをどう整理するかも大事。僕はよく、「読者の興味」「業界トピック」「媒体の目的」という3つの円を描いて、その重なりを探すようにしています。
これはいわば「手堅い」企画の作り方。 でも、すべてが重ならなくてもいい。
媒体としてのメッセージ性を打ち出したり、尖った企画で突破口を開いたりするときは、どこかの円に特化したほうがむしろいい場合もある。自分の置かれた立場と読者の顔を思い浮かべながら、この円を行ったり来たりするのが「企画を立てる」という作業なんじゃないでしょうか。
■「とりあえず考えてみる」を許そう
そして何よりも大事なのは、「ダメかも」と思う企画でも、とりあえず出してみること。企画って、机の上で一人きりで完結するものじゃなくて、誰かと会話することで磨かれていくことが多いんです。
だから、「一発で完璧を目指さない」こともすごく大事。
そもそも、いい企画が出るときって、大体が雑談の中や移動中、あるいはふとした瞬間にやってくるものです。頭の中の「いつかやりたい」フォルダにしまい込んだままじゃもったいない。まずは企画メモをどんどん書きためてみてください。量が質を生みます。
■最後に:「企画が立たない」と思っているあなたへ
「思いつかない」のは、思いつくための準備がまだ整っていないだけ。 情報を集めて、整理して、仮にでもいいから出してみる。 それだけで、企画はちゃんと「立って」くれます。
肩の力を抜いて、今日も一つ、企画のタネを拾いに行きませんか?
ど、どうでしょう。。?
僕の所感としては、率直に「すごいな」と思いました。「企画が思いつきません」の一言だけで、ここまで返してくれるのかと。
細部で「僕だったらそういういい方はしないかもな」「当時はそう思ったけど、今ならこう言うだろうな」と思う個所は確かにあるのですが、「過去に言った覚えのある事」がうまく使われている感じがします。すごい。
■過去の発言をなぞる発信は、自分でやらなくてもよくなる?
ここまでAIが仕上げてくれると、僕の仕事はもう
①僕らしい書き方へと微修正する
②"今の"僕だったらどうこたえるか、アップデート部分を追記する
みたいなところに収れんしていきます。
前者の「書き方」の部分はプロンプトの工夫や今後のAIの進化によってもっと磨かれていくと思うので、本当に本当に大事なのは②なんでしょうね。
以前、ライターや編集者がAIと向き合う上では「自己ベストを更新するような発信をしつづける姿勢」が大事だと書いてみたのですが、本当にそうだなと再認識しました(有料noteで恐縮です)。
■遺書を書くような気持ちで
話しはやや飛躍しますが、AIがここまで「僕っぽいアウトプット」を出せるようになってくると僕が仮にこの世を去っても、AIが「僕ならどう答えるか」を出してくれるようにもなるのだと思います。僕の子ども、そのあとの子孫にわたるまで、「まむし爺さんはこういう思想だったらしいぞ」と継承されていくのは、何だか不思議な構図です。
今書いているこの文章ですら、やがてAIに食われ、「僕っぽいアウトプットを出すための血肉」になっていくのだとすれば、今行っている一つ一つの発信って、後世への遺書みたいなものだなとも思うようになってきました。自分の思考のコピーがネット上に漂い続けるのだと思うと、生きる意味を残す意味でも発信活動を続けてみようかなと思ったりもします。いわゆる終活の一環として、「AIに思考を残しておく」みたいなことがありえるのかもなとか思ったりなどしました。
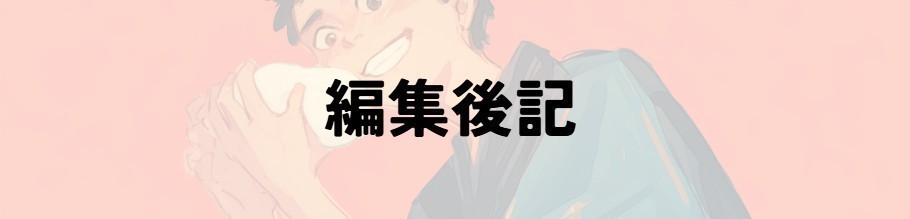
今回のニュースレターは、「アウトプットを豊富にしておけば、構成にもその考えを引き継ぐことができる…」という話でしたが、歴史上の偉人たちを召喚する作業なんかは、すでに結構できるんですよね。
アリストテレスや孫子などなど、多くの人に影響を与えた思想家たちをめぐってはいろんな書籍やネット上の考察があるので、いまさら何をインプットするまでもなく、「彼らだったらどう考えるか」を導き出すことができる状態にあります。
過去の知識を活かして、現代人がさらに新しい知識を得ることを「巨人の肩の上に立つ」と言いますが、まさにそんな感じ。一人では到達できなかったであろう、「もっと遠くの景色」が見られている感覚があります。

ご縁いただきまして、日本最大級のフリーランス・副業メディアであるWorkship MAGAZINEさんで連載させていただくことになりました!初回は、クライアントから「次もお願いしたい」と思われるためのポイントについて。
↓読んで感想などSNSでいただけると嬉しいっす!
すでに登録済みの方は こちら